
完熟きんかん「たまたま」ができるまで
日之影町地域おこし協力隊の工藤正臣です。今回は、町内で生産の盛んな完熟きんかん「たまたま」がどのように生産されているのか、1年間の流れを紹介します。
まず、3月に剪定(せんてい)を行います。人間に例えると散髪でしょうか。伸びた枝をカットしてさっぱり!太陽の光が全体に当たるように樹形を整えます。

4月になると新芽(枝や葉の赤ちゃん)がニョキニョキと出てきます。この頃は軟らかく、触ると簡単に折れてしまいます。

5月になると枝が伸びて硬くなり、葉色も濃くなります。

6月中旬から花芽(はなめ)が膨らみ始め、6月下旬から花が咲きます。花が咲いても気温などの条件が良くなければ、実にならずに花は落ちてしまいます。きんかんは、実が着くまで何度も花が咲くため、1番花(いちばんか)、2番花(にばんか)、3番花(さんばんか)・・・と呼んでいます。1番花と2番花でできるだけたくさんの実がなるように生産者の皆さんは温度管理などに気をつけています。


6月から7月に咲いた花の花びらが落ちた後、めしべの根元の子房(しぼう)が膨らみ、幼果(ようか)と呼ばれるきんかんの赤ちゃんができます。幼果は夏の太陽と水によってどんどん大きくなり、きんかんの果実へと成長します。


たくさんの実がなりますが、傷があるものを摘み取り(摘果)、きれいな実だけを残して大きくなるように管理します。果実は11月頃から少しずつ緑色がうすくなり、黄色、橙色に変化します。

6月下旬に咲いた花が1月下旬になると甘くておいしいきんかんになります。完熟きんかん「たまたま」は花から収穫まで7か月間(約210日)、暑さや台風などの苦難を乗り越え、宮崎の太陽を燦々(さんさん)と浴びながら、生産者の手間と愛情によっておいしくなっているのです。
また来年1月においしい完熟きんかん「たまたま」を全国のファンの皆さんに届けられるよう、今年も剪定作業が始まっています。













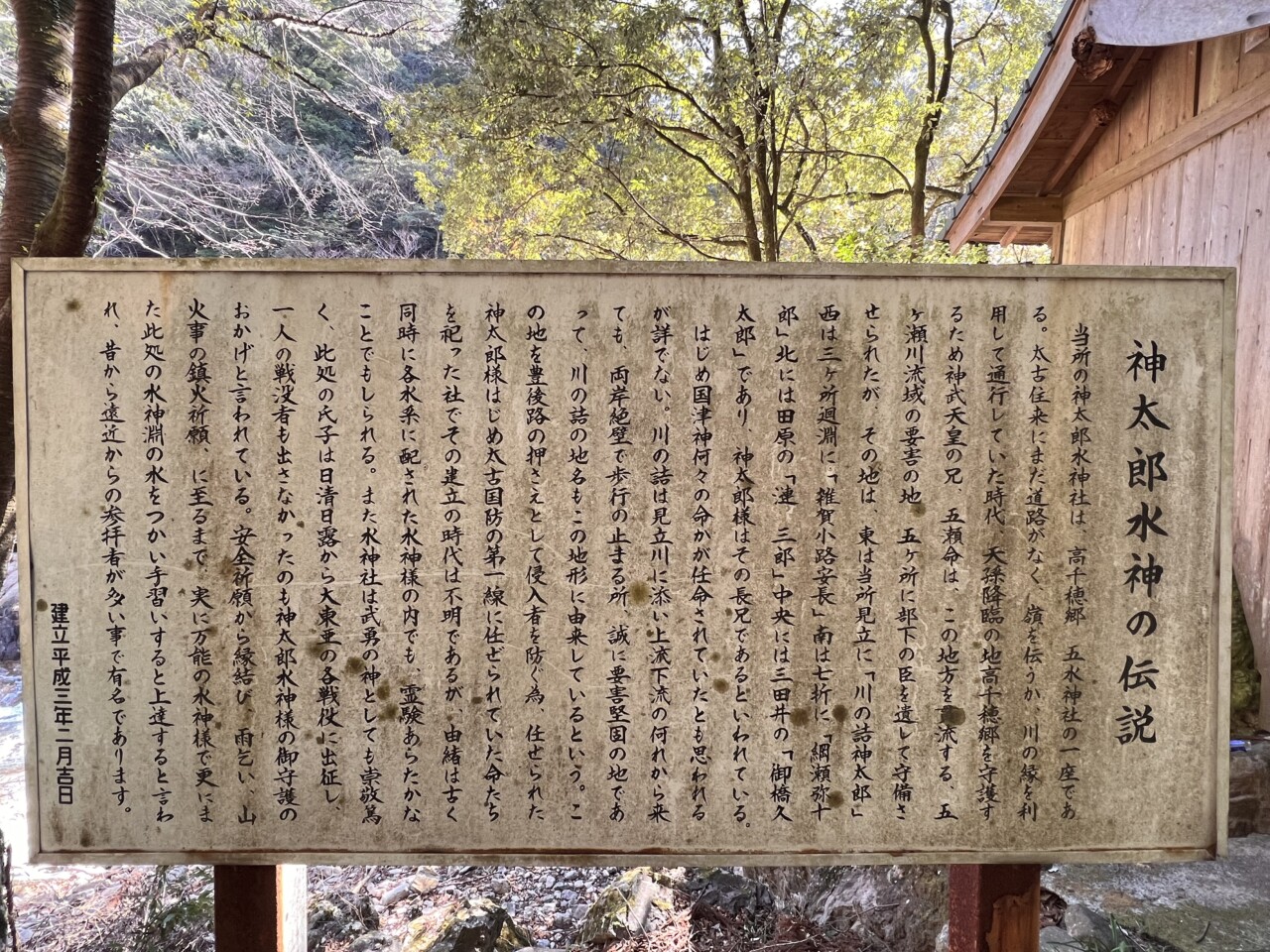

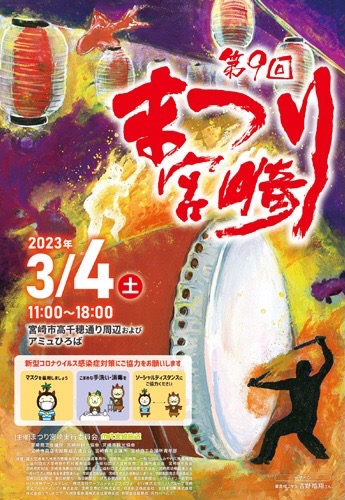









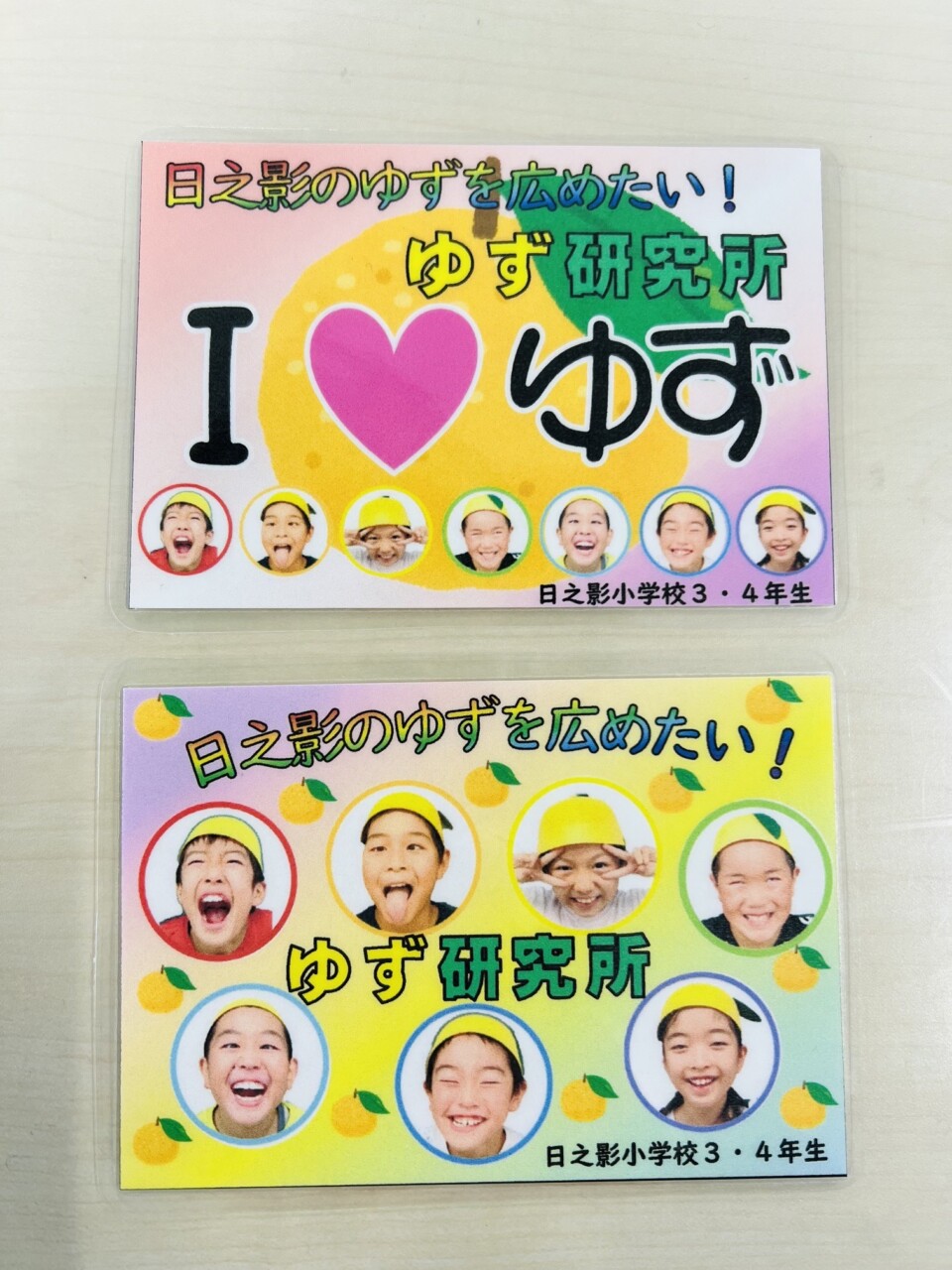







 さて、ここからが大変。ノミや彫刻刀、フックナイフを使い穴をくり抜いていきます。これも旋盤機があれば早いのでしょうが、それでは削る楽しみがない。グリーンなウッドワークじゃないわけです。
さて、ここからが大変。ノミや彫刻刀、フックナイフを使い穴をくり抜いていきます。これも旋盤機があれば早いのでしょうが、それでは削る楽しみがない。グリーンなウッドワークじゃないわけです。 血だらけですね。ナイフの先ちょが触れただけの怪我です。いつものことなのでご心配なく。
血だらけですね。ナイフの先ちょが触れただけの怪我です。いつものことなのでご心配なく。 指が入るくらいの穴を開けようとしたらでたらめなところで貫通してしまい。これ以上大きくできませんでした。
指が入るくらいの穴を開けようとしたらでたらめなところで貫通してしまい。これ以上大きくできませんでした。 手前のクポコはグリーンウッドワークの研修で作成したもの(材料は栗の木)。
手前のクポコはグリーンウッドワークの研修で作成したもの(材料は栗の木)。


